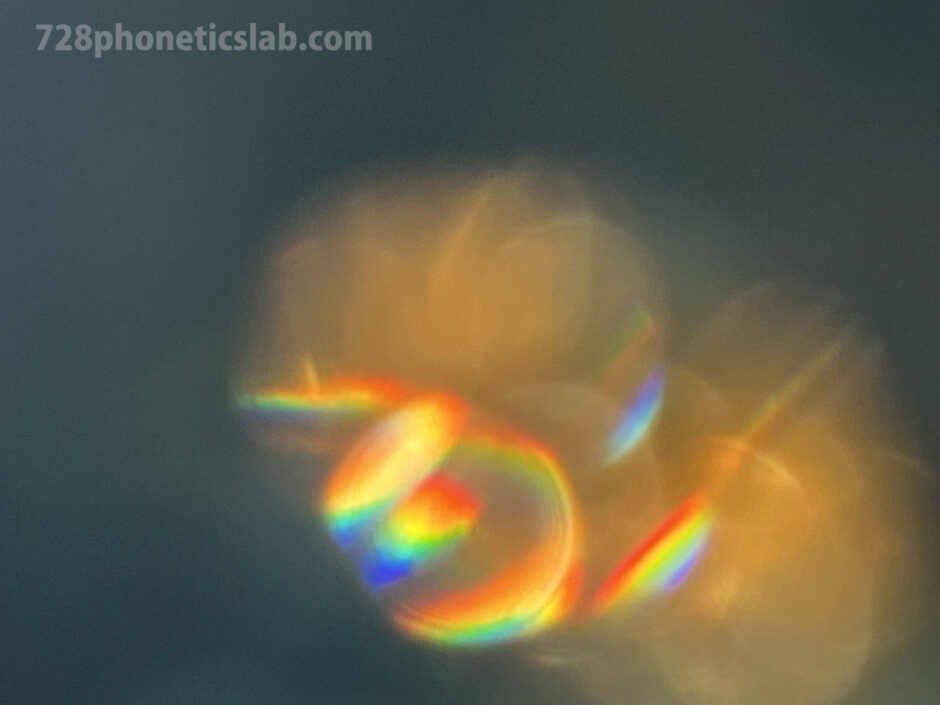音声学・音韻論的な面で言うと、有標性とは、言語音には一定の序列があり、基本的で簡単な音から複雑で難しい音まで様々なレベルのものがあるという概念で、基本的で簡単なものを「無標」、複雑で難しいものを「有標」と呼びます。
- 言語音には一定の序列がある:
・無標 = 基本的で簡単
・有標 = 複雑で難しい - 無標な音、有標な音の例(※「X < Y」は「Xの方がYよりも無標(Yの方がXよりも有標)」ということを表す)
・母音の場合・・・a, i, u < e, o < ü, öなど
・阻害音の場合・・・閉鎖音 < 摩擦音、破擦音
・共鳴音の場合・・・鼻音(m, nなど)、j(ヤ行音の子音), w < l, r
・etc. - 有標な音は無標な音に比べて:
・世界の言語の中で音素として出現しにくい
・幼児の獲得時期が遅い
・音の喪失(失語症等)において失われやすい
・etc. - 含意の法則:
・有標な音の存在は、無標な音の存在を含意する
無標な音は基本的で簡単であるがゆえに世界中の言語で頻繁に使われ、幼児が獲得する時期も早いのに対し、有標な音はその逆で限られた言語の中にしか出てこないし、幼児が獲得する時期も遅くなる傾向があります。
例えば、wはrよりも無標なので、英語を母語とする幼児はrよりも先にwを発音できるようになり、rの発音が正しくできないうちはrをwで置き換えて発音してしまったりします(日本人はlやrの発音が苦手ですが、これらの音は有標なので、実は英語圏の幼児にとっても難しいのです)。
同じような関係はtとs(tの方がsよりも無標)やdとz(dの方がzよりも無標)の間にも見られます(「ぞうさん」を「どうたん」と発音してしまうようなパターン)が、興味深いのは、逆の現象、つまり有標な音の代わりに無標な音で置き換えるような発音の誤りは起こらない(例えば、「とうさん」を「とうたん」(s → t)と発音してしまうミスは起こり得るが、「そうさん」(t → s)のように発音してしまうミスは基本ない)という点です。
以上のような特徴から、有標な音の存在は無標な音の存在を含意する(幼児の音韻獲得で言えば、ある幼児が無標な音を獲得できているとしても有標な音を獲得できているとは限らないが、有標な音を獲得している幼児は、それよりも無標な音を獲得できていると言える)ということになり、これが言語音における含意の法則などと呼ばれたりすることもあります。(言語音だとイメージがしにくい人は、縄跳びの二重跳びと三重跳びの関係を考えてみると理解しやすいかもしれません。一般的には、二重跳びの方が三重跳びよりも簡単なはずなので、できるようになる順序としては二重跳びが先、三重跳びが後になるのが普通で、二重跳びはできるが三重跳びは難しくてできないというパターンはあり得ますが、三重跳びができるのに二重跳びができないという状況は考えにくいわけで、それと同じようなことだと考えられます。)
有標性についてはまだまだ色々と書けることがあるので、いずれタイミングを見て追記していきたいと思います。
窪薗晴夫(1999)『日本語の音声』岩波書店.
McLeod, Sharynne (ed.) (2007). The International Guide to Speech Acquisition. New York: Thomson Delmar Learning.